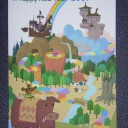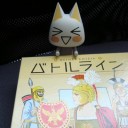お先にしつれいしま〜す (メビウス日本語訳付)
2011年12月7日 カードゲーム・ボードゲーム
残業を押しつけ合うカードゲーム。
ルールは簡単。
プレイ人数に応じた枚数のタイルを各自に配る。
タイルは両面印刷で、片側にキャラクターの顔、もう片側にそのキャラクターが何かしらの仕事をこなしている絵が描かれている。
それぞれ手元にタイルを並べてスタート。
タイルは最初、全てキャラクター面が表になっている状態から始まる。
一巡目は自分の手元にあるそのタイルをめくって仕事面にすることしかできない。
二巡目からはタイルをめくる以外に、別の手も行えるようになる。
めくったタイル同士で、キャラクターか仕事内容が一致しているものは、重ねて置くことができるのだ。つまり、仕事を押しつけるわけだ。
移動させる先は自分の手元にあるタイルでも、相手のところにあるタイルでも構わない。
重なったタイルはそっくりそのまままとめて移動することができるため、時間が経つにつれてうずたかく積もっていくことになる。
最終的に、手元にあるタイルが一番少ない人が勝ち。さっさと仕事を終えて「お先に失礼しまーす!!」というわけだ。
もちろんごっそり仕事を押しつけられた人が負け。
ルールはこれだけだし、プレイ時間も短い。長考する人がいると多少テンポは悪くなるが、それでも短い方だと思う。
4人までできるが未経験。友人と2人プレイ、3人プレイまでやったことがあるが、どちらとも実にあっさりと、それでいて面白くプレイできた。
友人も「もう一回、もう一回」と続けてプレイを要求してきたので、それなりに楽しんでいたものと思われる。
勝敗も偏ることなく、みんな等しく勝ち負けしていた。よっぽど読みがきくとかそういう人がいない限り、ある程度どんな人でも勝負になると思う。特に、人数が多くなると不確定要素が多くなってくるから、その傾向が強くなるのかな?
そんなにいっぱいやっているわけではないからわからないが。
お手軽にゲームなどで時間を潰したいという人にはお勧め。タイルを置いてプレイするので、場所が確保できるところじゃないとダメだけど。
クレーム処理とコピーと棚卸しと伝票整理をまとめて押しつけられたときの絶望感たらなかったね。最後の最後で。帰り支度してたのに。
ルールは簡単。
プレイ人数に応じた枚数のタイルを各自に配る。
タイルは両面印刷で、片側にキャラクターの顔、もう片側にそのキャラクターが何かしらの仕事をこなしている絵が描かれている。
それぞれ手元にタイルを並べてスタート。
タイルは最初、全てキャラクター面が表になっている状態から始まる。
一巡目は自分の手元にあるそのタイルをめくって仕事面にすることしかできない。
二巡目からはタイルをめくる以外に、別の手も行えるようになる。
めくったタイル同士で、キャラクターか仕事内容が一致しているものは、重ねて置くことができるのだ。つまり、仕事を押しつけるわけだ。
移動させる先は自分の手元にあるタイルでも、相手のところにあるタイルでも構わない。
重なったタイルはそっくりそのまままとめて移動することができるため、時間が経つにつれてうずたかく積もっていくことになる。
最終的に、手元にあるタイルが一番少ない人が勝ち。さっさと仕事を終えて「お先に失礼しまーす!!」というわけだ。
もちろんごっそり仕事を押しつけられた人が負け。
ルールはこれだけだし、プレイ時間も短い。長考する人がいると多少テンポは悪くなるが、それでも短い方だと思う。
4人までできるが未経験。友人と2人プレイ、3人プレイまでやったことがあるが、どちらとも実にあっさりと、それでいて面白くプレイできた。
友人も「もう一回、もう一回」と続けてプレイを要求してきたので、それなりに楽しんでいたものと思われる。
勝敗も偏ることなく、みんな等しく勝ち負けしていた。よっぽど読みがきくとかそういう人がいない限り、ある程度どんな人でも勝負になると思う。特に、人数が多くなると不確定要素が多くなってくるから、その傾向が強くなるのかな?
そんなにいっぱいやっているわけではないからわからないが。
お手軽にゲームなどで時間を潰したいという人にはお勧め。タイルを置いてプレイするので、場所が確保できるところじゃないとダメだけど。
クレーム処理とコピーと棚卸しと伝票整理をまとめて押しつけられたときの絶望感たらなかったね。最後の最後で。帰り支度してたのに。
1月20日の日記
2009年1月20日 カードゲーム・ボードゲーム
写真はすごろくやさんから届いた年賀はがきです。
ここ最近やりたいこと方面がこんがらがってる in my brain 状態で、にっちもさっちもいかなくなっていました。もうダメかと思うすんでの所までいつものたうち回って、灰になる直前に「あ、待てよ」と新たな可能性が生まれる感じです。
まるで手足を縛られて喉が渇いてどうしようもない自分に神様が焦らすように一滴一滴水を垂らしてくるような、そんな気分です。しんどい。
さて、とりあえず先日プレイしたカタンの感想でも。先日と言ってもだいぶ前ですが。
その前に、まず「ロボ77」と「バトルライン」について軽く。
友人Aとは今までバトルラインで遊んでいたんですが、友人Bには教えていなかったので、今回レクチャー。
素人だから成せるような大胆な打ち筋に新鮮な驚きを感じる自分と友人A。というか、それが単に彼の性質なのだろうか。今後慣れていく過程でどういうプレイになっていくのかちょっと面白いです。
「ロボ77」もレクチャー。
やはり、Bも結構焦って、ハラハラしていた模様。このゲームは時間制限ルールを設けるだけでもやはりかなりパーティゲームとしての盛り上がりの貢献すると思います。ルールも簡単だし。
ただし、単調なので永遠続けられるような質のもではないし、脱落方式なので、先に負けた人が若干暇になってしまうと言う欠点もあります。外野から試合にのめり込んでいればいいのですが。
そして「カタン」リベンジ。
前回ルールを間違えていた所為で中弛み感があったので、今回果たしてどうなるか。
前回間違えた箇所は盗賊のバーストルール。サイコロを振って合計が7になると、本当はカードを8枚以上持っている人が半分にしなければいけなくなると言うところを、全員必ず半分にしていたわけです。元々7は出やすい数字の上、前回は3回振って1回は盗賊みたいな高頻度だったため、全然資源が集まらないと言うことに。
また、みんなルールが朧だったため、初期配置も資源の産出しにくいところばかりに置いてしまって、二重苦だったわけです。今回は皆その点も踏まえて配置。
盗賊もそれほど出ず、皆順調に資源が集まり、道路を造ったり家を建てたり。
自分は初期配置の沿岸から道路を延ばしまくり、ロンゲストロードをゲット。友人Aは2つの初期配置の家と道路が近く、広く拡大すると言うよりはまとまって狭く厚くする戦術。特定のサイコロの目が出るとモッサモッサ資源が取れる(笑
Bは離して置いた初期配置の家と道路双方にバランス良く投資。途中、道路を繋げられて、ロンゲストロードをBに取られる。
負けじと自分も伸ばしに伸ばしまくって奪い返す(笑
結局最終的に自分が先に10ポイント獲得して終了。
前回よりは格段にゲームらしいゲームが出来た気がします。が、感想としては何だかいまいち盛り上がりに欠けたような気がする。
メンバーに闘争心が足りないのか(笑)、駆け引きが未熟なのか、ほとんど波乱もなく、そのまま予定調和みたいな感じで終わってしまった。
うーむ。
今後、無理矢理何回もプレイをお願いして、みんなに慣れていって貰うしかないのだろうか?
昨年辺りからドイツ発中心のボード・カードゲームに魅力を感じ、色々面白そうなのがあるなあと物色しているのだけど、買うときにはネットの評価だけでなく、色々と考慮して買わないといけないなあ。
「サメ警報」とか、「ゴキブリポーカー」とかちょっと敬遠してたんだけど、意外とこういうのの方がいいのかもしれない。わからないけど。
ここ最近やりたいこと方面がこんがらがってる in my brain 状態で、にっちもさっちもいかなくなっていました。もうダメかと思うすんでの所までいつものたうち回って、灰になる直前に「あ、待てよ」と新たな可能性が生まれる感じです。
まるで手足を縛られて喉が渇いてどうしようもない自分に神様が焦らすように一滴一滴水を垂らしてくるような、そんな気分です。しんどい。
さて、とりあえず先日プレイしたカタンの感想でも。先日と言ってもだいぶ前ですが。
その前に、まず「ロボ77」と「バトルライン」について軽く。
友人Aとは今までバトルラインで遊んでいたんですが、友人Bには教えていなかったので、今回レクチャー。
素人だから成せるような大胆な打ち筋に新鮮な驚きを感じる自分と友人A。というか、それが単に彼の性質なのだろうか。今後慣れていく過程でどういうプレイになっていくのかちょっと面白いです。
「ロボ77」もレクチャー。
やはり、Bも結構焦って、ハラハラしていた模様。このゲームは時間制限ルールを設けるだけでもやはりかなりパーティゲームとしての盛り上がりの貢献すると思います。ルールも簡単だし。
ただし、単調なので永遠続けられるような質のもではないし、脱落方式なので、先に負けた人が若干暇になってしまうと言う欠点もあります。外野から試合にのめり込んでいればいいのですが。
そして「カタン」リベンジ。
前回ルールを間違えていた所為で中弛み感があったので、今回果たしてどうなるか。
前回間違えた箇所は盗賊のバーストルール。サイコロを振って合計が7になると、本当はカードを8枚以上持っている人が半分にしなければいけなくなると言うところを、全員必ず半分にしていたわけです。元々7は出やすい数字の上、前回は3回振って1回は盗賊みたいな高頻度だったため、全然資源が集まらないと言うことに。
また、みんなルールが朧だったため、初期配置も資源の産出しにくいところばかりに置いてしまって、二重苦だったわけです。今回は皆その点も踏まえて配置。
盗賊もそれほど出ず、皆順調に資源が集まり、道路を造ったり家を建てたり。
自分は初期配置の沿岸から道路を延ばしまくり、ロンゲストロードをゲット。友人Aは2つの初期配置の家と道路が近く、広く拡大すると言うよりはまとまって狭く厚くする戦術。特定のサイコロの目が出るとモッサモッサ資源が取れる(笑
Bは離して置いた初期配置の家と道路双方にバランス良く投資。途中、道路を繋げられて、ロンゲストロードをBに取られる。
負けじと自分も伸ばしに伸ばしまくって奪い返す(笑
結局最終的に自分が先に10ポイント獲得して終了。
前回よりは格段にゲームらしいゲームが出来た気がします。が、感想としては何だかいまいち盛り上がりに欠けたような気がする。
メンバーに闘争心が足りないのか(笑)、駆け引きが未熟なのか、ほとんど波乱もなく、そのまま予定調和みたいな感じで終わってしまった。
うーむ。
今後、無理矢理何回もプレイをお願いして、みんなに慣れていって貰うしかないのだろうか?
昨年辺りからドイツ発中心のボード・カードゲームに魅力を感じ、色々面白そうなのがあるなあと物色しているのだけど、買うときにはネットの評価だけでなく、色々と考慮して買わないといけないなあ。
「サメ警報」とか、「ゴキブリポーカー」とかちょっと敬遠してたんだけど、意外とこういうのの方がいいのかもしれない。わからないけど。
コメントをみる | 

12月19日の日記
2008年12月19日 カードゲーム・ボードゲーム・バトルライン
以前「バトルライン」を紹介したときに少しルールを間違えて書いていたと思われます。
「証明」ルールなのですが、以前は確か、手番中であればいつでも「証明」ができ、成立した暁には相手のターンを経てフラッグを確保できる、と言う風に書いたような記憶があります。
しかし実際は基本的に証明ができた時点でその場のフラッグを確保できるらしいのです。つまり、証明して、相手のターンを経ることがないので、戦術カードで覆されることはないわけです。相手のターンを経るのは、引き分けで決着した場合に限ります。
次にアドバンスルール、と言うものがあります。若干制限を加えたルールですね。このルールによると、証明を含めたフラッグの確保は手番の一番始めにしかできない、と言うことになっています。つまり、自分がカードを置いてからは証明できない。証明できるようにカードを配置して、相手のターンを経て自分の手番の最初に証明する。その事によって初めてフラッグを確保できるわけです。
相手が気付かなければそのまま確保できますが、相手に気付かれると戦術カードで対応される可能性が出てきます。またこれは3対3の直接対決時にも当てはまります。あくまで確保は自分の手番の最初の行為でなければならないのです。
今まで自分がやっていた独自のルールは証明を宣言して相手番を経るので、相手に否が応でも気付かれてしまったわけです。が、既存のアドバンスルールは証明を指摘しないので、こちらは気付かれる可能性が減るし、相手は(と言うかお互いに)場のカード全体に注意を払っていないといけない、と言うことになるわけです。
まあどっちにしろ、疲れることに変わりはないですけどね。
・開拓ゲームカタン・スタンダード
大航海時代、カタンと呼ばれる島が発見され、次々入植が始まった。
そして人々は先に10ポイント獲得して勝利するため(10ポイントって何だ?)、開拓競争が始まる。
と言うのが筋書き。
ゲームの内容はひたすら資源を集め、足りない資源はトレードで手に入れ、何ならチャンスカードで有利な状況を作りつつ、道を引き、家を造って10ポイントを目指す、というもの。
ボードゲームではかなり人気があるみたいですね。
先日初めてプレイしましたがルールをいまいちはっきり把握しないまま行ってしまったのでダメでした。盗賊を移動した後、8枚以上手札を持っている人は半分に減らさないといけないルールがあるのですが、枚数関係なく(少ない手札でも)半分にしてしまい、全然資源が集まらなかったり。そのくせ盗賊の出現は多いので中弛み感が発生してしまいました。
あと、ボードは厚紙のような物なのですが、型から外すときに多少折れ曲がってしまうらしく、ボードを組み合わせたときにガタガタになってしまいました。まあこれは調節して何とかなりましたけど。
もう一回しっかりした知識で始めたいですね。ルールが把握できれば結構楽しめるのかなと思います。カード枚数半減の所の間違いを改善するだけでも全然違うと思います。
以前「バトルライン」を紹介したときに少しルールを間違えて書いていたと思われます。
「証明」ルールなのですが、以前は確か、手番中であればいつでも「証明」ができ、成立した暁には相手のターンを経てフラッグを確保できる、と言う風に書いたような記憶があります。
しかし実際は基本的に証明ができた時点でその場のフラッグを確保できるらしいのです。つまり、証明して、相手のターンを経ることがないので、戦術カードで覆されることはないわけです。相手のターンを経るのは、引き分けで決着した場合に限ります。
次にアドバンスルール、と言うものがあります。若干制限を加えたルールですね。このルールによると、証明を含めたフラッグの確保は手番の一番始めにしかできない、と言うことになっています。つまり、自分がカードを置いてからは証明できない。証明できるようにカードを配置して、相手のターンを経て自分の手番の最初に証明する。その事によって初めてフラッグを確保できるわけです。
相手が気付かなければそのまま確保できますが、相手に気付かれると戦術カードで対応される可能性が出てきます。またこれは3対3の直接対決時にも当てはまります。あくまで確保は自分の手番の最初の行為でなければならないのです。
今まで自分がやっていた独自のルールは証明を宣言して相手番を経るので、相手に否が応でも気付かれてしまったわけです。が、既存のアドバンスルールは証明を指摘しないので、こちらは気付かれる可能性が減るし、相手は(と言うかお互いに)場のカード全体に注意を払っていないといけない、と言うことになるわけです。
まあどっちにしろ、疲れることに変わりはないですけどね。
・開拓ゲームカタン・スタンダード
大航海時代、カタンと呼ばれる島が発見され、次々入植が始まった。
そして人々は先に10ポイント獲得して勝利するため(10ポイントって何だ?)、開拓競争が始まる。
と言うのが筋書き。
ゲームの内容はひたすら資源を集め、足りない資源はトレードで手に入れ、何ならチャンスカードで有利な状況を作りつつ、道を引き、家を造って10ポイントを目指す、というもの。
ボードゲームではかなり人気があるみたいですね。
先日初めてプレイしましたがルールをいまいちはっきり把握しないまま行ってしまったのでダメでした。盗賊を移動した後、8枚以上手札を持っている人は半分に減らさないといけないルールがあるのですが、枚数関係なく(少ない手札でも)半分にしてしまい、全然資源が集まらなかったり。そのくせ盗賊の出現は多いので中弛み感が発生してしまいました。
あと、ボードは厚紙のような物なのですが、型から外すときに多少折れ曲がってしまうらしく、ボードを組み合わせたときにガタガタになってしまいました。まあこれは調節して何とかなりましたけど。
もう一回しっかりした知識で始めたいですね。ルールが把握できれば結構楽しめるのかなと思います。カード枚数半減の所の間違いを改善するだけでも全然違うと思います。
12月1日の日記
2008年12月1日 カードゲーム・ボードゲーム
先日購入したカードゲームの内、「ロボ77」と「バトルライン」を友人とプレイしました。
最初あまり乗り気ではないような感じだったけど、遊んでみると結構乗ってくれました。それはこの間の両親と同じ。やっぱり、面白い物は遊んでみると人を引き込みますね。友人と二人プレイでした。
・「ロボ77」(LOBO77)
ロボ77はかなりサクサク短時間で遊べるタイプなので、人数が少ない場合は予め配るコインの枚数を多くしたり、あるいは77以上になった場合にコイン全部没収ではなく、一枚の没収で済ませても良いと思います。
このゲーム、カードを一枚プレイしたあと一枚山札から補充しなければいけないわけですが、自分が引くのを忘れてしまい、次の人がカードをプレイしてしまうと、そのまま少ない手札で進めなければいけないのです。手札が少ないと言うことはその分選べるカードが少なくなるわけで、このゲームでは結構致命的です。
77以上になったときにラウンドが終了するので、ルール通りで行けば手札は回収され、また規定枚数配られることになるのですが、友人の案で、ラウンドが終了しても手札は回収せずそのまま少ない手札をペナルティとして継続するという鬼畜ルールを採用したりしました。
自分の考えた時間制限ルール、今回は5秒にしてみました。まあこれくらいが妥当でしょうか。きつい場合は7秒くらいにしても良いかもしれません。そこはさじ加減ですね。友人はこの時間制限ルールがスパイスとして効いているとして評価していました。
実際かなりエキサイティングしますよ。焦りますからね。しかもカウントや数字の合計など、基本的に口に出しますから、結構わいわい盛り上がれるゲームだと思います。普段クールな人でも、意外に熱くなってしまうゲームではないでしょうか。
・バトルライン
さて、打って変わって黙り込んでしまうゲームがこちら、バトルラインです。
これは完全に二人対戦用のゲームです。好評らしく、日本語版が出ています。実際遊んでみると非常に面白いです。このゲームのルールを考えた人は神なのではないか、と言うくらいに絶妙なゲームバランスになっています。
ただしルールなのですが、紙一枚の両面にびっしりと書き込まれているので、最初にとっかかる時にそれを覚えたりするのが大変かな、と言う印象です。でもまず一回ザッと読んで、あとは実際に確認しながらプレーしていくとあっさりと覚えられました。それどころか、戦略性の奥深さがみるみるわかってきて、かなり興奮してしまいました。
このゲームは旗取りゲームです。
9個の駒(フラッグと呼ぶ)を横一列で並べます。プレーヤーはそのフラッグを挟んで向かい合い、手札をフラッグごとにプレイ(置く)していきます。
カードは6色の数字カード1~10(計60枚)で、一つのフラッグに3枚まで置くことができます。その3枚の組み合わせによって役の強さが決まり、相手の役と比較して勝敗を決するわけです。先に連続したフラッグを3つ取るか、全体の中から5つ取ることによって勝利となります。
役は以下のようになっています。後になるほど弱くなります。
「同色の連番3枚」「多色の同数3枚」「同色の3枚」「多色の連番3枚」「ばらばら」
相手と役が一緒の場合は数字の合計で比較します。更にそれでも一緒の場合は引き分けです。その場合、役の完成が遅かった人が負けになります。
3枚しかカードを出せないので、2枚目を出した時点でおおかた相手の役がわかってしまいますし、1枚目の時点でもかなり制限がかかるのです。早くにカードを出しすぎると相手に対応されますし、かといって遅くなると引き分けの時やフラッグの数が減ったときなどに不利になる(フラッグの確保が遅れたりする)。
基本的にパスはやむを得ない場合を除いてできないので、一手一手確実なプレーが要求されるわけです。
更に洞察力も必要になります。
勝敗は必ずしも両者がカードを3枚ずつ出さなくても決することができるからです。
それは、自分の組んだ3枚のカードが絶対に相手に勝てる事を、その場にプレイされた全てのカードの範囲内で「証明」できればいいのです。
例えば自分が「青色の1,2,3」を出していたとします。相手は「赤色の2,3」を出していた。このとき場のどこかに「赤色の4」が出ていれば、自分が絶対に勝てることを「証明」できます。
というのは、自分は「同色の連番」という一番強い役を完成しているので、相手も同等以上にするためには絶対に「同色の連番」にしなければいけなくなっています。そのためには「赤の1か4」どちらかをプレイしなければいけないわけです。
しかし「赤の1」では、同じ役である上に、数字の合計も同数で引き分けとなります。引き分けの場合は遅れて完成させた(させることになる)プレーヤーの負けですので、絶対に「赤の4」を出すしかない。しかし、「赤の4」はすでに場に出されているので、「赤の2,3,4」が完成することはあり得ない。よって、相手に勝てる見込みが無くなったわけです。
この「証明」によって自分の勝ちが決まり、戦術カードによって状況が覆されない限り、次の自分のターンでフラッグが確保されるのです。
戦いはどちらかというと、この証明の方が重要になってくるのだと思います。相手の出すカードをよく観察して、自分にとってさほど重要ではなくとも(むしろいらないカードでも)、相手にとって重要であるようなカードをあえて自陣内にプレイすることにより、証明に持ち込んで勝利できるからです。自分が役を完成させ、証明できる状況を作ったり発見したりしておけば、相手の完成を待たずに勝てる。これは、先にフラッグを多く取った方が勝ちという意味においては、結構大きいのではないかと思うのです。
ただし「証明」した場合、次の自分の番にフラッグが確保されるわけです。つまり、一度相手の番を経て、と言うことです。その時に怖いのが「戦術カード」です。
戦術カードはいわゆる特殊カードで、様々な効果があります。
好きな色と数字を選べる(いわゆるジョーカーのような)リーダーカードや、役を無視して戦いを数字の合計だけに帰させる霧カードなどです。いずれも強力な効果があります。
しかしここも絶妙なのですが、この戦術カードは、相手の使用した戦術カードプラス1枚までしか使うことができないのです。つまり、相手が0回の使用ならば自分は1枚目まで、自分が1枚目を使用していれば相手は2枚目まで使用できるということです。
カードをプレイしたときに数字カードか戦術カードかどちらか一枚を補充できるのですが、戦術カードばかり補充しても相手が使用しなければこちらも使用できないわけで、ただのいらないカードになってしまいます。あるいは、相手に使わせないために自分も使わないということもできるわけです。
この点でも駆け引きがあるわけですね。
友人とは計10回近く……は言い過ぎとしても、6,7回はプレーしました。一番最初は負けましたが、その後は何とか全て勝利できました。彼は大変悔しがっていて、結構のめり込んでいる様子でしたね。いや、わかるわかる。これ凄く面白いっすよ。
ただしね、凄く疲れますよ。最初っから悩みっぱなしで。友人と自分は共に長考派だったので、おそらくワンプレー30~50分ほどかかってしまいました。もう、口数は極端に減りましたからね。ははは。
いや、このゲームは素晴らしいですよ。奇跡です。
最初あまり乗り気ではないような感じだったけど、遊んでみると結構乗ってくれました。それはこの間の両親と同じ。やっぱり、面白い物は遊んでみると人を引き込みますね。友人と二人プレイでした。
・「ロボ77」(LOBO77)
ロボ77はかなりサクサク短時間で遊べるタイプなので、人数が少ない場合は予め配るコインの枚数を多くしたり、あるいは77以上になった場合にコイン全部没収ではなく、一枚の没収で済ませても良いと思います。
このゲーム、カードを一枚プレイしたあと一枚山札から補充しなければいけないわけですが、自分が引くのを忘れてしまい、次の人がカードをプレイしてしまうと、そのまま少ない手札で進めなければいけないのです。手札が少ないと言うことはその分選べるカードが少なくなるわけで、このゲームでは結構致命的です。
77以上になったときにラウンドが終了するので、ルール通りで行けば手札は回収され、また規定枚数配られることになるのですが、友人の案で、ラウンドが終了しても手札は回収せずそのまま少ない手札をペナルティとして継続するという鬼畜ルールを採用したりしました。
自分の考えた時間制限ルール、今回は5秒にしてみました。まあこれくらいが妥当でしょうか。きつい場合は7秒くらいにしても良いかもしれません。そこはさじ加減ですね。友人はこの時間制限ルールがスパイスとして効いているとして評価していました。
実際かなりエキサイティングしますよ。焦りますからね。しかもカウントや数字の合計など、基本的に口に出しますから、結構わいわい盛り上がれるゲームだと思います。普段クールな人でも、意外に熱くなってしまうゲームではないでしょうか。
・バトルライン
さて、打って変わって黙り込んでしまうゲームがこちら、バトルラインです。
これは完全に二人対戦用のゲームです。好評らしく、日本語版が出ています。実際遊んでみると非常に面白いです。このゲームのルールを考えた人は神なのではないか、と言うくらいに絶妙なゲームバランスになっています。
ただしルールなのですが、紙一枚の両面にびっしりと書き込まれているので、最初にとっかかる時にそれを覚えたりするのが大変かな、と言う印象です。でもまず一回ザッと読んで、あとは実際に確認しながらプレーしていくとあっさりと覚えられました。それどころか、戦略性の奥深さがみるみるわかってきて、かなり興奮してしまいました。
このゲームは旗取りゲームです。
9個の駒(フラッグと呼ぶ)を横一列で並べます。プレーヤーはそのフラッグを挟んで向かい合い、手札をフラッグごとにプレイ(置く)していきます。
カードは6色の数字カード1~10(計60枚)で、一つのフラッグに3枚まで置くことができます。その3枚の組み合わせによって役の強さが決まり、相手の役と比較して勝敗を決するわけです。先に連続したフラッグを3つ取るか、全体の中から5つ取ることによって勝利となります。
役は以下のようになっています。後になるほど弱くなります。
「同色の連番3枚」「多色の同数3枚」「同色の3枚」「多色の連番3枚」「ばらばら」
相手と役が一緒の場合は数字の合計で比較します。更にそれでも一緒の場合は引き分けです。その場合、役の完成が遅かった人が負けになります。
3枚しかカードを出せないので、2枚目を出した時点でおおかた相手の役がわかってしまいますし、1枚目の時点でもかなり制限がかかるのです。早くにカードを出しすぎると相手に対応されますし、かといって遅くなると引き分けの時やフラッグの数が減ったときなどに不利になる(フラッグの確保が遅れたりする)。
基本的にパスはやむを得ない場合を除いてできないので、一手一手確実なプレーが要求されるわけです。
更に洞察力も必要になります。
勝敗は必ずしも両者がカードを3枚ずつ出さなくても決することができるからです。
それは、自分の組んだ3枚のカードが絶対に相手に勝てる事を、その場にプレイされた全てのカードの範囲内で「証明」できればいいのです。
例えば自分が「青色の1,2,3」を出していたとします。相手は「赤色の2,3」を出していた。このとき場のどこかに「赤色の4」が出ていれば、自分が絶対に勝てることを「証明」できます。
というのは、自分は「同色の連番」という一番強い役を完成しているので、相手も同等以上にするためには絶対に「同色の連番」にしなければいけなくなっています。そのためには「赤の1か4」どちらかをプレイしなければいけないわけです。
しかし「赤の1」では、同じ役である上に、数字の合計も同数で引き分けとなります。引き分けの場合は遅れて完成させた(させることになる)プレーヤーの負けですので、絶対に「赤の4」を出すしかない。しかし、「赤の4」はすでに場に出されているので、「赤の2,3,4」が完成することはあり得ない。よって、相手に勝てる見込みが無くなったわけです。
この「証明」によって自分の勝ちが決まり、戦術カードによって状況が覆されない限り、次の自分のターンでフラッグが確保されるのです。
戦いはどちらかというと、この証明の方が重要になってくるのだと思います。相手の出すカードをよく観察して、自分にとってさほど重要ではなくとも(むしろいらないカードでも)、相手にとって重要であるようなカードをあえて自陣内にプレイすることにより、証明に持ち込んで勝利できるからです。自分が役を完成させ、証明できる状況を作ったり発見したりしておけば、相手の完成を待たずに勝てる。これは、先にフラッグを多く取った方が勝ちという意味においては、結構大きいのではないかと思うのです。
ただし「証明」した場合、次の自分の番にフラッグが確保されるわけです。つまり、一度相手の番を経て、と言うことです。その時に怖いのが「戦術カード」です。
戦術カードはいわゆる特殊カードで、様々な効果があります。
好きな色と数字を選べる(いわゆるジョーカーのような)リーダーカードや、役を無視して戦いを数字の合計だけに帰させる霧カードなどです。いずれも強力な効果があります。
しかしここも絶妙なのですが、この戦術カードは、相手の使用した戦術カードプラス1枚までしか使うことができないのです。つまり、相手が0回の使用ならば自分は1枚目まで、自分が1枚目を使用していれば相手は2枚目まで使用できるということです。
カードをプレイしたときに数字カードか戦術カードかどちらか一枚を補充できるのですが、戦術カードばかり補充しても相手が使用しなければこちらも使用できないわけで、ただのいらないカードになってしまいます。あるいは、相手に使わせないために自分も使わないということもできるわけです。
この点でも駆け引きがあるわけですね。
友人とは計10回近く……は言い過ぎとしても、6,7回はプレーしました。一番最初は負けましたが、その後は何とか全て勝利できました。彼は大変悔しがっていて、結構のめり込んでいる様子でしたね。いや、わかるわかる。これ凄く面白いっすよ。
ただしね、凄く疲れますよ。最初っから悩みっぱなしで。友人と自分は共に長考派だったので、おそらくワンプレー30~50分ほどかかってしまいました。もう、口数は極端に減りましたからね。ははは。
いや、このゲームは素晴らしいですよ。奇跡です。
コメントをみる | 

11月14日の日記
2008年11月14日 カードゲーム・ボードゲーム
カードゲームを買いました。カードゲームと言ってもトレーディングカードと言った類ではなく、トランプのように、それ一式あれば遊べるタイプの物です。一部の好評を博した物は追加キットのような物があるらしいですが、基本的にはそれだけで遊べます。
「すごろくや」さんで買いました。写真は届いた紙袋に印刷されていたネズミでちゅー。
「すごろくや」さん(http://sugorokuya.jp/)
本当はメビウスゲームズさんで買おうと思ったんですが、ちょうどお店の連休と重なってしまったので、今回はすごろくやさんにお世話になりました。
メビウスゲームズさん(http://www.mobius-games.co.jp/)
で、買ったゲームは4つ。
・LOBO77(http://www.mobius-games.co.jp/Amigo/Lobo77.html)
・ニムト(http://www.mobius-games.co.jp/Amigo/6nimmt.htm)
・バトルライン(http://ejf.cside.ne.jp/review/battleline.html)
・迷宮牧場の決闘(http://sgrk.blog53.fc2.com/?no=721)
ロボ77は一度親とやってみました。
大雑把なルールは、手持ちのカードは数字カードと特殊カードの二種類で計五枚。カードを一枚ずつ順番に場に出してその時の合計数を口に出して言う。
例えば場に「5」のカードが置かれていて、自分が「4」のカードを出したら、合計は「9」なので、「きゅう」と言いながら出すわけです。
そうやって足したり引いたりしていくのですが、各自チップが配られていて、数字の合計をぞろ目にしてしまった人はチップ一枚をマイナスされる。77以上の数字にしてしまった人は手持ちのチップ全てを没収されて、そのラウンドは終了。
チップを持っていない人がチップを出さなければ行けない状況になった場合、その人はチップを払えないので脱落です。最後まで残った人が勝ち。
時間制限をつけないと手持ちのカードをどのタイミングで出すのか戦略を考えやすいですが、その分計算に時間を割けるのでぞろ目の回数は若干減ります。
なので独自のルールとして、計算をシビアにするために時間制限をつけました。自分がやったときは3秒のカウント内にカードをプレイしなければチップを一枚支払うことにしました。ただちょっとこれはシビアすぎる気がしたので、5秒ぐらいが適当かと。
あと、計算が間違っていた場合、次の人がカードをプレイする前に誰かがそのミスを指摘すれば、間違えた人がチップマイナス1枚のペナルティを受けることにしました。
さらに、その指摘自体が間違いだったとき(つまり、前のプレーヤーが計算を間違えていない場合)は、指摘ミスをした人がチップマイナス一枚としました。
手番になったときにそれまでの合計数を記憶し、かつ自分のカードとの計算、ぞろ目や77以上になるかならないかの配慮、そして口に出して言う、という一連の作業を制限時間内に行わなければいけないので、結構間違えやすいんですよね。焦って。
しかも、前の人が計算を間違えていないか確認する事も含めるともうわけがわからなくなります。
今回は両親と3人でプレーしましたが、結構盛り上がりました。計算の苦手な低脳家族ですので(苦笑)
ゲーム自体は最高で8人までプレイできるようです。
今度はニムトなども含めて友人とやってみたいなと思います。まあ、いつになるかはわからないですがね。
「すごろくや」さんで買いました。写真は届いた紙袋に印刷されていたネズミでちゅー。
「すごろくや」さん(http://sugorokuya.jp/)
本当はメビウスゲームズさんで買おうと思ったんですが、ちょうどお店の連休と重なってしまったので、今回はすごろくやさんにお世話になりました。
メビウスゲームズさん(http://www.mobius-games.co.jp/)
で、買ったゲームは4つ。
・LOBO77(http://www.mobius-games.co.jp/Amigo/Lobo77.html)
・ニムト(http://www.mobius-games.co.jp/Amigo/6nimmt.htm)
・バトルライン(http://ejf.cside.ne.jp/review/battleline.html)
・迷宮牧場の決闘(http://sgrk.blog53.fc2.com/?no=721)
ロボ77は一度親とやってみました。
大雑把なルールは、手持ちのカードは数字カードと特殊カードの二種類で計五枚。カードを一枚ずつ順番に場に出してその時の合計数を口に出して言う。
例えば場に「5」のカードが置かれていて、自分が「4」のカードを出したら、合計は「9」なので、「きゅう」と言いながら出すわけです。
そうやって足したり引いたりしていくのですが、各自チップが配られていて、数字の合計をぞろ目にしてしまった人はチップ一枚をマイナスされる。77以上の数字にしてしまった人は手持ちのチップ全てを没収されて、そのラウンドは終了。
チップを持っていない人がチップを出さなければ行けない状況になった場合、その人はチップを払えないので脱落です。最後まで残った人が勝ち。
時間制限をつけないと手持ちのカードをどのタイミングで出すのか戦略を考えやすいですが、その分計算に時間を割けるのでぞろ目の回数は若干減ります。
なので独自のルールとして、計算をシビアにするために時間制限をつけました。自分がやったときは3秒のカウント内にカードをプレイしなければチップを一枚支払うことにしました。ただちょっとこれはシビアすぎる気がしたので、5秒ぐらいが適当かと。
あと、計算が間違っていた場合、次の人がカードをプレイする前に誰かがそのミスを指摘すれば、間違えた人がチップマイナス1枚のペナルティを受けることにしました。
さらに、その指摘自体が間違いだったとき(つまり、前のプレーヤーが計算を間違えていない場合)は、指摘ミスをした人がチップマイナス一枚としました。
手番になったときにそれまでの合計数を記憶し、かつ自分のカードとの計算、ぞろ目や77以上になるかならないかの配慮、そして口に出して言う、という一連の作業を制限時間内に行わなければいけないので、結構間違えやすいんですよね。焦って。
しかも、前の人が計算を間違えていないか確認する事も含めるともうわけがわからなくなります。
今回は両親と3人でプレーしましたが、結構盛り上がりました。計算の苦手な低脳家族ですので(苦笑)
ゲーム自体は最高で8人までプレイできるようです。
今度はニムトなども含めて友人とやってみたいなと思います。まあ、いつになるかはわからないですがね。