12月1日の日記
2008年12月1日 カードゲーム・ボードゲーム
先日購入したカードゲームの内、「ロボ77」と「バトルライン」を友人とプレイしました。
最初あまり乗り気ではないような感じだったけど、遊んでみると結構乗ってくれました。それはこの間の両親と同じ。やっぱり、面白い物は遊んでみると人を引き込みますね。友人と二人プレイでした。
・「ロボ77」(LOBO77)
ロボ77はかなりサクサク短時間で遊べるタイプなので、人数が少ない場合は予め配るコインの枚数を多くしたり、あるいは77以上になった場合にコイン全部没収ではなく、一枚の没収で済ませても良いと思います。
このゲーム、カードを一枚プレイしたあと一枚山札から補充しなければいけないわけですが、自分が引くのを忘れてしまい、次の人がカードをプレイしてしまうと、そのまま少ない手札で進めなければいけないのです。手札が少ないと言うことはその分選べるカードが少なくなるわけで、このゲームでは結構致命的です。
77以上になったときにラウンドが終了するので、ルール通りで行けば手札は回収され、また規定枚数配られることになるのですが、友人の案で、ラウンドが終了しても手札は回収せずそのまま少ない手札をペナルティとして継続するという鬼畜ルールを採用したりしました。
自分の考えた時間制限ルール、今回は5秒にしてみました。まあこれくらいが妥当でしょうか。きつい場合は7秒くらいにしても良いかもしれません。そこはさじ加減ですね。友人はこの時間制限ルールがスパイスとして効いているとして評価していました。
実際かなりエキサイティングしますよ。焦りますからね。しかもカウントや数字の合計など、基本的に口に出しますから、結構わいわい盛り上がれるゲームだと思います。普段クールな人でも、意外に熱くなってしまうゲームではないでしょうか。
・バトルライン
さて、打って変わって黙り込んでしまうゲームがこちら、バトルラインです。
これは完全に二人対戦用のゲームです。好評らしく、日本語版が出ています。実際遊んでみると非常に面白いです。このゲームのルールを考えた人は神なのではないか、と言うくらいに絶妙なゲームバランスになっています。
ただしルールなのですが、紙一枚の両面にびっしりと書き込まれているので、最初にとっかかる時にそれを覚えたりするのが大変かな、と言う印象です。でもまず一回ザッと読んで、あとは実際に確認しながらプレーしていくとあっさりと覚えられました。それどころか、戦略性の奥深さがみるみるわかってきて、かなり興奮してしまいました。
このゲームは旗取りゲームです。
9個の駒(フラッグと呼ぶ)を横一列で並べます。プレーヤーはそのフラッグを挟んで向かい合い、手札をフラッグごとにプレイ(置く)していきます。
カードは6色の数字カード1~10(計60枚)で、一つのフラッグに3枚まで置くことができます。その3枚の組み合わせによって役の強さが決まり、相手の役と比較して勝敗を決するわけです。先に連続したフラッグを3つ取るか、全体の中から5つ取ることによって勝利となります。
役は以下のようになっています。後になるほど弱くなります。
「同色の連番3枚」「多色の同数3枚」「同色の3枚」「多色の連番3枚」「ばらばら」
相手と役が一緒の場合は数字の合計で比較します。更にそれでも一緒の場合は引き分けです。その場合、役の完成が遅かった人が負けになります。
3枚しかカードを出せないので、2枚目を出した時点でおおかた相手の役がわかってしまいますし、1枚目の時点でもかなり制限がかかるのです。早くにカードを出しすぎると相手に対応されますし、かといって遅くなると引き分けの時やフラッグの数が減ったときなどに不利になる(フラッグの確保が遅れたりする)。
基本的にパスはやむを得ない場合を除いてできないので、一手一手確実なプレーが要求されるわけです。
更に洞察力も必要になります。
勝敗は必ずしも両者がカードを3枚ずつ出さなくても決することができるからです。
それは、自分の組んだ3枚のカードが絶対に相手に勝てる事を、その場にプレイされた全てのカードの範囲内で「証明」できればいいのです。
例えば自分が「青色の1,2,3」を出していたとします。相手は「赤色の2,3」を出していた。このとき場のどこかに「赤色の4」が出ていれば、自分が絶対に勝てることを「証明」できます。
というのは、自分は「同色の連番」という一番強い役を完成しているので、相手も同等以上にするためには絶対に「同色の連番」にしなければいけなくなっています。そのためには「赤の1か4」どちらかをプレイしなければいけないわけです。
しかし「赤の1」では、同じ役である上に、数字の合計も同数で引き分けとなります。引き分けの場合は遅れて完成させた(させることになる)プレーヤーの負けですので、絶対に「赤の4」を出すしかない。しかし、「赤の4」はすでに場に出されているので、「赤の2,3,4」が完成することはあり得ない。よって、相手に勝てる見込みが無くなったわけです。
この「証明」によって自分の勝ちが決まり、戦術カードによって状況が覆されない限り、次の自分のターンでフラッグが確保されるのです。
戦いはどちらかというと、この証明の方が重要になってくるのだと思います。相手の出すカードをよく観察して、自分にとってさほど重要ではなくとも(むしろいらないカードでも)、相手にとって重要であるようなカードをあえて自陣内にプレイすることにより、証明に持ち込んで勝利できるからです。自分が役を完成させ、証明できる状況を作ったり発見したりしておけば、相手の完成を待たずに勝てる。これは、先にフラッグを多く取った方が勝ちという意味においては、結構大きいのではないかと思うのです。
ただし「証明」した場合、次の自分の番にフラッグが確保されるわけです。つまり、一度相手の番を経て、と言うことです。その時に怖いのが「戦術カード」です。
戦術カードはいわゆる特殊カードで、様々な効果があります。
好きな色と数字を選べる(いわゆるジョーカーのような)リーダーカードや、役を無視して戦いを数字の合計だけに帰させる霧カードなどです。いずれも強力な効果があります。
しかしここも絶妙なのですが、この戦術カードは、相手の使用した戦術カードプラス1枚までしか使うことができないのです。つまり、相手が0回の使用ならば自分は1枚目まで、自分が1枚目を使用していれば相手は2枚目まで使用できるということです。
カードをプレイしたときに数字カードか戦術カードかどちらか一枚を補充できるのですが、戦術カードばかり補充しても相手が使用しなければこちらも使用できないわけで、ただのいらないカードになってしまいます。あるいは、相手に使わせないために自分も使わないということもできるわけです。
この点でも駆け引きがあるわけですね。
友人とは計10回近く……は言い過ぎとしても、6,7回はプレーしました。一番最初は負けましたが、その後は何とか全て勝利できました。彼は大変悔しがっていて、結構のめり込んでいる様子でしたね。いや、わかるわかる。これ凄く面白いっすよ。
ただしね、凄く疲れますよ。最初っから悩みっぱなしで。友人と自分は共に長考派だったので、おそらくワンプレー30~50分ほどかかってしまいました。もう、口数は極端に減りましたからね。ははは。
いや、このゲームは素晴らしいですよ。奇跡です。
最初あまり乗り気ではないような感じだったけど、遊んでみると結構乗ってくれました。それはこの間の両親と同じ。やっぱり、面白い物は遊んでみると人を引き込みますね。友人と二人プレイでした。
・「ロボ77」(LOBO77)
ロボ77はかなりサクサク短時間で遊べるタイプなので、人数が少ない場合は予め配るコインの枚数を多くしたり、あるいは77以上になった場合にコイン全部没収ではなく、一枚の没収で済ませても良いと思います。
このゲーム、カードを一枚プレイしたあと一枚山札から補充しなければいけないわけですが、自分が引くのを忘れてしまい、次の人がカードをプレイしてしまうと、そのまま少ない手札で進めなければいけないのです。手札が少ないと言うことはその分選べるカードが少なくなるわけで、このゲームでは結構致命的です。
77以上になったときにラウンドが終了するので、ルール通りで行けば手札は回収され、また規定枚数配られることになるのですが、友人の案で、ラウンドが終了しても手札は回収せずそのまま少ない手札をペナルティとして継続するという鬼畜ルールを採用したりしました。
自分の考えた時間制限ルール、今回は5秒にしてみました。まあこれくらいが妥当でしょうか。きつい場合は7秒くらいにしても良いかもしれません。そこはさじ加減ですね。友人はこの時間制限ルールがスパイスとして効いているとして評価していました。
実際かなりエキサイティングしますよ。焦りますからね。しかもカウントや数字の合計など、基本的に口に出しますから、結構わいわい盛り上がれるゲームだと思います。普段クールな人でも、意外に熱くなってしまうゲームではないでしょうか。
・バトルライン
さて、打って変わって黙り込んでしまうゲームがこちら、バトルラインです。
これは完全に二人対戦用のゲームです。好評らしく、日本語版が出ています。実際遊んでみると非常に面白いです。このゲームのルールを考えた人は神なのではないか、と言うくらいに絶妙なゲームバランスになっています。
ただしルールなのですが、紙一枚の両面にびっしりと書き込まれているので、最初にとっかかる時にそれを覚えたりするのが大変かな、と言う印象です。でもまず一回ザッと読んで、あとは実際に確認しながらプレーしていくとあっさりと覚えられました。それどころか、戦略性の奥深さがみるみるわかってきて、かなり興奮してしまいました。
このゲームは旗取りゲームです。
9個の駒(フラッグと呼ぶ)を横一列で並べます。プレーヤーはそのフラッグを挟んで向かい合い、手札をフラッグごとにプレイ(置く)していきます。
カードは6色の数字カード1~10(計60枚)で、一つのフラッグに3枚まで置くことができます。その3枚の組み合わせによって役の強さが決まり、相手の役と比較して勝敗を決するわけです。先に連続したフラッグを3つ取るか、全体の中から5つ取ることによって勝利となります。
役は以下のようになっています。後になるほど弱くなります。
「同色の連番3枚」「多色の同数3枚」「同色の3枚」「多色の連番3枚」「ばらばら」
相手と役が一緒の場合は数字の合計で比較します。更にそれでも一緒の場合は引き分けです。その場合、役の完成が遅かった人が負けになります。
3枚しかカードを出せないので、2枚目を出した時点でおおかた相手の役がわかってしまいますし、1枚目の時点でもかなり制限がかかるのです。早くにカードを出しすぎると相手に対応されますし、かといって遅くなると引き分けの時やフラッグの数が減ったときなどに不利になる(フラッグの確保が遅れたりする)。
基本的にパスはやむを得ない場合を除いてできないので、一手一手確実なプレーが要求されるわけです。
更に洞察力も必要になります。
勝敗は必ずしも両者がカードを3枚ずつ出さなくても決することができるからです。
それは、自分の組んだ3枚のカードが絶対に相手に勝てる事を、その場にプレイされた全てのカードの範囲内で「証明」できればいいのです。
例えば自分が「青色の1,2,3」を出していたとします。相手は「赤色の2,3」を出していた。このとき場のどこかに「赤色の4」が出ていれば、自分が絶対に勝てることを「証明」できます。
というのは、自分は「同色の連番」という一番強い役を完成しているので、相手も同等以上にするためには絶対に「同色の連番」にしなければいけなくなっています。そのためには「赤の1か4」どちらかをプレイしなければいけないわけです。
しかし「赤の1」では、同じ役である上に、数字の合計も同数で引き分けとなります。引き分けの場合は遅れて完成させた(させることになる)プレーヤーの負けですので、絶対に「赤の4」を出すしかない。しかし、「赤の4」はすでに場に出されているので、「赤の2,3,4」が完成することはあり得ない。よって、相手に勝てる見込みが無くなったわけです。
この「証明」によって自分の勝ちが決まり、戦術カードによって状況が覆されない限り、次の自分のターンでフラッグが確保されるのです。
戦いはどちらかというと、この証明の方が重要になってくるのだと思います。相手の出すカードをよく観察して、自分にとってさほど重要ではなくとも(むしろいらないカードでも)、相手にとって重要であるようなカードをあえて自陣内にプレイすることにより、証明に持ち込んで勝利できるからです。自分が役を完成させ、証明できる状況を作ったり発見したりしておけば、相手の完成を待たずに勝てる。これは、先にフラッグを多く取った方が勝ちという意味においては、結構大きいのではないかと思うのです。
ただし「証明」した場合、次の自分の番にフラッグが確保されるわけです。つまり、一度相手の番を経て、と言うことです。その時に怖いのが「戦術カード」です。
戦術カードはいわゆる特殊カードで、様々な効果があります。
好きな色と数字を選べる(いわゆるジョーカーのような)リーダーカードや、役を無視して戦いを数字の合計だけに帰させる霧カードなどです。いずれも強力な効果があります。
しかしここも絶妙なのですが、この戦術カードは、相手の使用した戦術カードプラス1枚までしか使うことができないのです。つまり、相手が0回の使用ならば自分は1枚目まで、自分が1枚目を使用していれば相手は2枚目まで使用できるということです。
カードをプレイしたときに数字カードか戦術カードかどちらか一枚を補充できるのですが、戦術カードばかり補充しても相手が使用しなければこちらも使用できないわけで、ただのいらないカードになってしまいます。あるいは、相手に使わせないために自分も使わないということもできるわけです。
この点でも駆け引きがあるわけですね。
友人とは計10回近く……は言い過ぎとしても、6,7回はプレーしました。一番最初は負けましたが、その後は何とか全て勝利できました。彼は大変悔しがっていて、結構のめり込んでいる様子でしたね。いや、わかるわかる。これ凄く面白いっすよ。
ただしね、凄く疲れますよ。最初っから悩みっぱなしで。友人と自分は共に長考派だったので、おそらくワンプレー30~50分ほどかかってしまいました。もう、口数は極端に減りましたからね。ははは。
いや、このゲームは素晴らしいですよ。奇跡です。
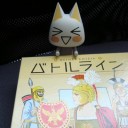


コメント